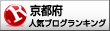京都の観光スポットと人気のトップ争いを続けている清水寺、9月の風景です。紅葉シーズンは年間で最も賑やかになりますが、いまは嵐の前の静けさですね。そうはいっても門前は観光客でいっぱいです。

以前は紅葉前の9月、10月は京都観光の穴場だったのですが、いまはシーズンはありませんね。本日は境内で秋の「青龍会」が開催されるためでしょうか。やや多めに感じます。

見渡すと観光客の80%くらいが海外からの観光客のように見受けられます。伏見稲荷といい清水寺といい朱色に塗られたこれらの建物が皆さんお好きなようで。

清水寺の本堂は現在50年ぶりの「平成大修理」が行われています。2017年にスタートし2021年の完了の予定、4年かけての工事です。檜皮屋根の吹き替えなどを行います。素屋根(建物全体を覆う工事用の建造物)ですっぽり覆われ、本堂が覆い隠されています。

これまで東本願寺や知恩院のような大伽藍の改修工事用の素屋根をいくつか見てきましたが、通常は鉄骨の骨組みで支えられ巨大な体育館のようなもの。ところが清水寺の素屋根は丸太を組み合わせる伝統的な工法です。

改修工事中も本堂内には入ることができ、舞台の先端に行くこともできます。また御本尊の参拝もできます。

奥の院から本堂の素屋根を眺めたところ。

少し狭くなってはいますが舞台の先端で絶景を眺めることができますね。

今回はショートカットコース、本堂わきの長階段を降ります。素屋根用の木組みを近くで見るためです。

降りたところにある音羽の滝は相変わらず人気ですね。いつも耐えない行列。

下から見上げると、すごい迫力。そもそも清水寺の本堂と舞台は傾斜地に建てられているので、鉄骨の素屋根を建設することができなかったのかもしれません。何百年も受け継がれてきた清水寺オンリーの修復の技を目の当たりに見ることが出来るのですね。

いったん仁王門まで降りて再び参道にもどり、拝観受付の手前までやってきました。ここで向かって左側を眺めると立派なもんが見えます。これは「北総門」(重要文化財)、清水寺の塔頭・成就院の正門として建造されたものです。

そして北総門の向かって右手にあるのが弁天池と弁天堂です。

さらに北総門の手前に小さな観音様。

「ぬれて観世音」(濡れ手観音)といいます。以前は「奥之院」の裏にあったものが移設されました。この観音様に水をかけることによって煩悩が洗い流される、といいます。自身が水行によって願いを成就すべきところ、観音様が身代わりのなって水行をしてくれる。水掛けはそのお手伝いです。

すわ、濃霧?! いえいえミストです。雨の日にミストは必要ないと思うのですが(汗)。

|
|