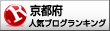ウイークデーの観光オフシーズン、前日の申し込みで仙洞御所の参観が出来ました。参観は一日二回、11時からと13時半からです。私たちは午前に参加しました。

出発10分前に集合。スタートまでの待ち時間は待合室で苑内紹介のビデオを見ます。今日の参加者は20名弱、少なめです。

大宮御所の「御車寄」です。三重の屋根が特徴。
最初に説明員から「説明には興味ない、写真を取りたい、という方はどうぞご自由に。」という言葉に励まされて思う存分撮影しました。

大宮御所への潜戸を潜る前の苔庭です。

「大宮御殿」、天皇皇后が京都に来られるときに宿泊される場所です。左が紅梅、右が白梅です。好天に恵まれラッキーでした。

大宮御所の敷地から庭園にでると目の前に「北池」が広がります。東山が借景です。木々と東山の間には京都府立病院や京都大学などのビルが立ち並んでいるのですが、うまく隠されています。


最初に渡る橋です。名前は「六枚橋」。右手は「阿古瀬淵」

野鳥や水鳥を眺めながら北池の周りをぐるっと散策します。

いいながめです! 二つの橋が重なって見えますね。手前が「紅葉橋」むこうが「八ツ橋」。北池と南池をつなぐ水路の部分です。

ふたつ目に渡った橋は「土橋」

3つ目は「石橋」

4つ目は対岸から見えた「紅葉橋」。紅葉シーズンはきれいだろうなぁ。

布落ちする「雄滝」、高さ180cm

藤棚で覆われた「八ツ橋」です。いただいたパンフレットの写真では藤の花が満開でした。

八橋を渡ったところにあった「雪見灯籠」、対岸に醒花亭がみえています。

洲浜の縁に立つ「醒花亭」、屋根は2日前の雪で覆われています。

洲浜の玉石は全部で11万1千個。1個につき米1升の約束で同じ大きさの石を集めたのだとか。

「醒花亭」はベンガラ色が基調の茶亭です。正面玄関には庇をつけ、障子は腰高。独特の作りです。

醒花亭の「醒花」は李白の詩から取られたもの。

東の庭には加藤清正の献上品と言われる朝鮮燈籠と、「ふくろう」の銘のある手水鉢が据えられています。

これは「古墳」らしい。

「以前は氷室と思われていましたが、どうもそうではないことが分かり、今では説明の対象になっていません。」と説明がありました。

「柿本人磨呂神社」、火除として祀られているそうです。「人麻呂」=「火止まる」だそうです。

洲浜に沿ってのびるまっすぐな道は「桜の馬場」と呼ばれます。

京都洛中の真ん中にこんな場所があるとは驚きです。ハイシーズンでなければ参観申し込みも難しくなさそうですので四季を通じて参観してみたくなりました。今回は「冬の仙洞御所」でした。

|
|