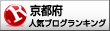深緑の季節、青もみじを求めて神護寺を訪問しました。

梅雨入り前で空気はさわやかですが、やはり一汗かきますね。何度見ても神々しい「楼門」前の風景です。1623年の建立。

広い境内も緑が深くなっています。


「金堂」は比較的新しく1934年の建立。中にはいると空気はひんやり。

手前は「毘沙門堂」、むこうは「五大堂」、どちらも1623年の建立。

「多宝塔」金堂の背後に建ちます。1934年の建立。

手摺りの向こうに向かって「かわらけ」を投げ、厄除けします。かわらけ投げは、神護寺が発祥とされています。

100円で小さなかわらけが2枚渡されます。風に乗れば遠くまで飛びますが、なかなか難しい。


「和気公霊廟」と後ろは「鐘楼」

「鐘楼」は1623年の建立。国宝の梵鐘を収めます。875年の作。橘広相、菅原是善、藤原敏行の3人の文人による命が残っていて「三絶の鐘」と称されています。

和気清麻呂の墓をこれからお参りします。

このような気持ちの良い山道を5分ほど歩いた小高いところにお墓がありました。


これが和気清麻呂のお墓です。神護寺に参拝しても、ここまで来る参拝者はまずありません。

Ads by Google
|
|